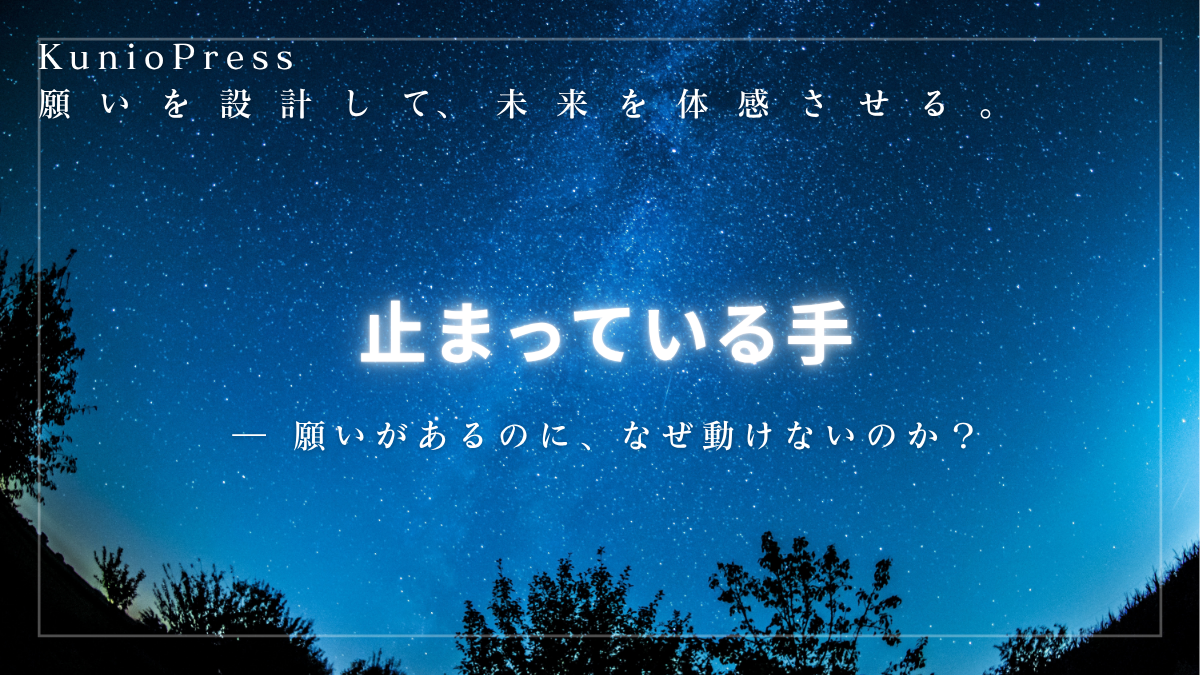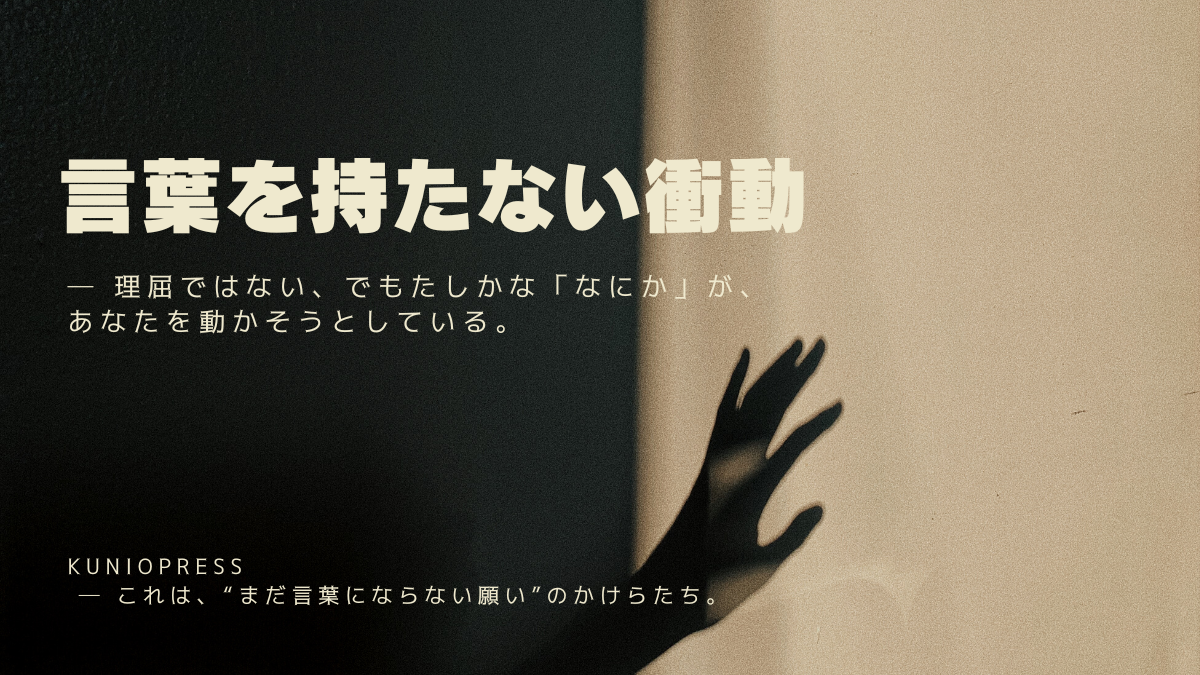― 願いがあるのに、なぜ動けないのか?
はじめに
「やりたい気持ちはある」
でも、手が止まってしまっている。
気づけば、時間だけが過ぎていく。
それは意志が弱いわけじゃない。
あなたの中にまだ、設計図が描けていないだけかもしれません。
この場所では、止まってしまった“その手”に、
もう一度あたたかく触れなおすところから始めていきます。
動けないのは「根っこ」が曖昧だからかもしれない
よくある誤解のひとつ:
「動けないのは気合が足りないせい」
→ ✖️ そうではありません。
こんな状態、心当たりありませんか?
| 状態 | 内側で起きていること |
|---|---|
| やりたいことが多すぎて絞れない | 本質的な願いがまだ整理されていない |
| 完璧を求めて最初の一歩が踏み出せない | 失敗のイメージばかりが先行している |
| 誰かの正解に合わせすぎて疲れている | 自分の軸がまだ持てていない |
まず「設計図」を描くことから始めよう
止まってしまったときこそ、勢いより構造が必要です。
「何を」「なぜ」「どうやって」やるのか?
この順番で考えてみると、意外なほど整理が進みます。
シンプルなフレームワーク
- 願いの核(Why)
── 本当は何を大切にしたいのか? - 手段の仮説(What)
── それを叶える方法の候補は何か? - 最小の一歩(How)
── いますぐ試せる小さな行動は?
✔︎「正解」を探すよりも、
✔︎「仮説」で試していくことが大切です。
自分の“設計視点”を手に入れる問い
以下のような問いを、ノートに書いてみましょう:
自分の奥にある願いを掘る問い
- 「もし失敗しないとしたら、何をしてみたい?」
- 「誰のどんな生き方に、嫉妬を感じる?」
- 「本当は、どんな日々を送りたい?」
行動に落とすための問い
- 「この願いを1%だけ進めるとしたら?」
- 「10分でできる行動は?」
- 「“やらなくていいこと”は何だろう?」
手が止まっているときの“対処法リスト”
| 症状 | 試してみたい処方箋 |
|---|---|
| 何から始めればいいかわからない | まず「問い」を書き出す |
| 完璧に仕上げようとして動けない | 仮のアウトプットを出す |
| モヤモヤして集中できない | 散歩や声に出すことで外に出す |
| SNSで他人と比べて焦る | 一度、入力を止めて「自分の出力」に集中 |
自分で設計する力を、取り戻す
誰かに作られた「完成形」に乗るのではなく、
自分で地図を描くことが、願いを現実にしていく道です。
そしてその地図は、
・感情の記録
・問いのメモ
・試してみた行動のログ
といった、とても地味な“作業”の中から生まれます。
「設計する力」は、じつは誰にでも備わっている。
ただそれを、使ってこなかっただけかもしれません。
おわりに
願いはあるのに、動けない。
そんなとき、自分を責めるのではなく、
「まだ設計ができていないだけ」と思ってみてください。
止まっている手には、動き出す準備がもう宿っている。
それに気づけたとき、新しい一歩は自然と始まります。