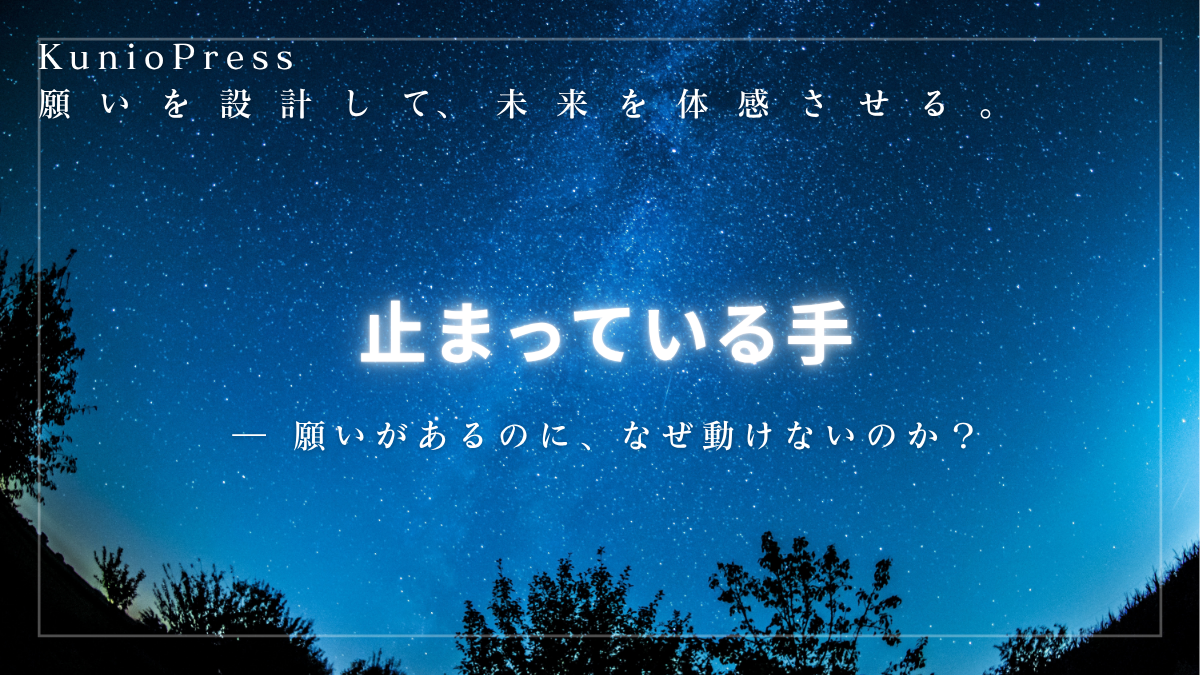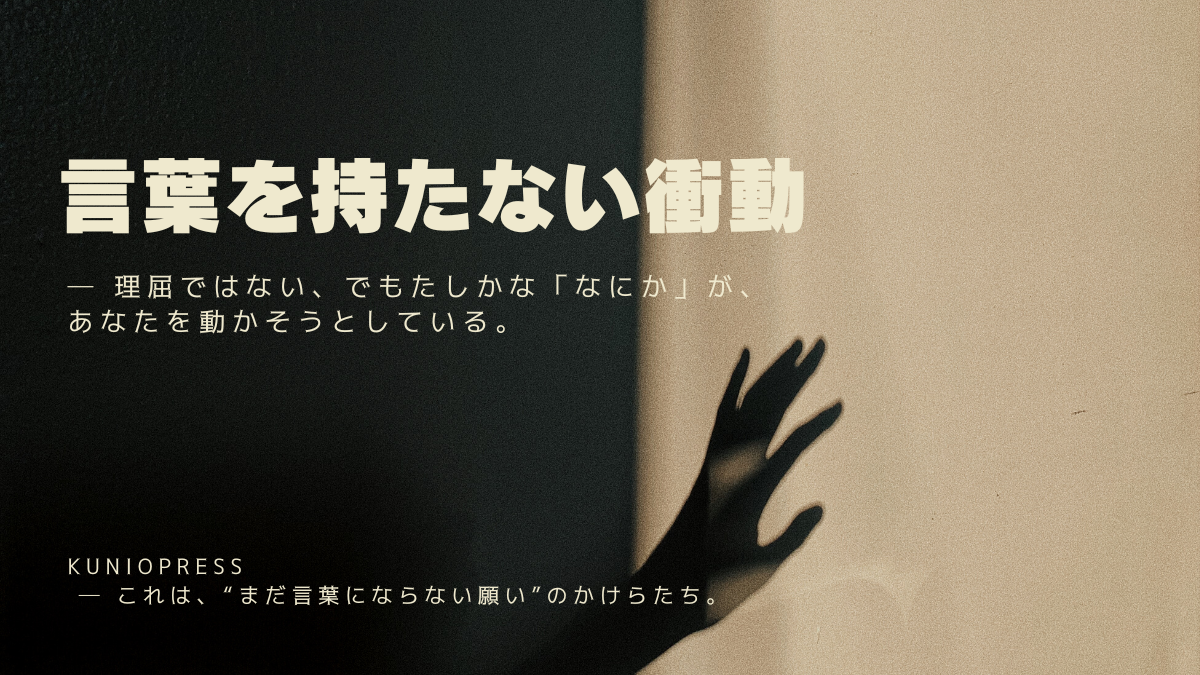──「どちらでもなく、どちらでもある」わたしを肯定する物語
1. はじめに ― 曖昧さは、弱さではない
「わたしはどこに属しているのだろう?」
「はっきりとした輪郭を持てないまま、何かの“あいだ”に立っている気がする。」
それはきっと、あなたの中に“感知できてしまうもの”が多すぎるから。
でも、大丈夫。
この境界に立つということは、他の誰にも見えない微細な変化や、
ことばにされる前の空気の震えを感じ取れるということでもあるのです。
2. 境界にいるということ
境界とは、
- 白と黒のあいだの 灰色のニュアンス
- 安心と不安の はざまにある静けさ
- 選びきれない自分を そのまま引き受ける場所
その場所に立っていることに、
確信を持てなくて当然です。
でもそれがあなたの感性の深さであり、変化の前触れなのです。
3. 見えにくい「立ち位置」の中で
あなたが感じる「どっちつかず」や「宙ぶらりん」は、
社会のルールに“ぴたりと合わない”違和感でもあるでしょう。
でもそれは、こうも言えます:
🌱 どちらにも染まらないからこそ、<br>両方を翻訳できる「通訳者」になれる。
4. あなたの感受性が世界に与えているもの
あなたは…
- 誰かの曖昧な感情を、言葉になる前に察している
- どちらか一方の視点だけでなく、両方の立場に立とうとしている
- 人の間に起こる緊張感を、自分の責任のように感じてしまう
それは疲れることもあります。
でも、あなたがいることで世界は 対立を越えて接続されるのです。
5. 曖昧さを抱くあなたへの問いかけ
- 「わからないままでも、大切なものってあるだろうか?」
- 「名前のない感覚を、誰かと共有できるだろうか?」
- 「“選ばない勇気”って、あっていいのだろうか?」
その問いのひとつひとつが、
あなたらしさを照らすランプです。
6. 生きづらさは、才能の裏返し
| 感じていること | 実はあなたのギフト |
|---|---|
| はっきり言い切れない | 多角的に物事を見られる |
| ひとに流されやすい | 他者の気配を察知できる感度がある |
| 境界がわからず不安になる | 自他を分けずに共感できる力を持っている |
7. 曖昧さを育てる、5つの視点
- 決めつけずに保留する
「まだわからない」ことをそのままにしておく強さを育てる。 - 対立より“翻訳”を選ぶ
意見の違いを調整する言葉を編む練習をしてみる。 - 自分の曖昧さを許可する
「私ってこういうとこもあるよね」と受け入れる。 - 安心できるあいまいな関係を持つ
はっきりさせすぎない居場所や人間関係も大事にする。 - “言葉にならない感情”を表現に変える
絵、詩、音、身体表現などで外に出すこと。
8. 境界に立つあなたに伝えたいこと
あなたの居場所は、たしかにあります。
それは「外側」ではなく、曖昧なあなた自身の中にあるのです。
明確さばかりが求められるこの時代に、
輪郭のあいまいなあなたは、“未来”をつなぐ存在。
誰でもない自分を選ぶこと。
そのことが、誰かの安心にもなるのです。